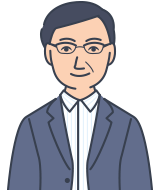- 詳細解説
- 業界別IoTシステムの活用例
第2回
建設DXの実践によって、人手不足・低生産性・脱炭素化を解決
建設業界では慢性的な人手不足が深刻です。なかなか進まない生産性の向上にも悩まされており、これは、建設に携わるあらゆる関係者が直面している問題です。
さらに近年、脱炭素化への対応も求められるようになり、建設業界は仕事の進め方を改善する必要に迫られています。
今回は、これらの課題を解決するためのデジタル技術とデータ活用などについて、事例を交えながら解説します。

新しいビルや建物、道路などが建設されている様子を見ると、これから街がどう変わるのか、気持ちがワクワクしてくる人は多いのではないでしょうか。建設業界は、社会の豊かさを象徴する業種の代表と言えるでしょう。その発展は、すなわち社会活動や暮らしの発展につながります。
ところが、そんな建設業界は、現在、継続的成長を阻む課題に直面しています。慢性的な人手不足や、なかなか進まない生産性の向上、脱炭素化への対応などです。
近年、これらの解決を目指して、デジタル技術を活用した「建設デジタルトランスフォーメーション(DX)」に取り組む建設会社や建材・住宅設備などのサプライヤが増えてきています。
人手不足、低い生産性に加え、脱炭素化に向けた施策も必須に
建設業界は慢性的な人手不足の状態にあり、早急な対処が求められています。国土交通省によると、ピークだった1997年時点の建設業の就業者数は685万人でしたが、その後右肩下がりに減り続け、2021年には482万人と大きく減少したと言います。しかも、年齢階層別の建設技能者数の調査では、その25.7%が60歳以上であり、15歳から29歳以下の若い世代は12.0%しかいない状態で、明らかな高齢化が進んでいます。こうした状況の背景には、社会全体の少子高齢化が進んでいるのと同時に、“3K(きつい、汚い、危険)職場”というイメージがある旧来の建設業界に若者が魅力を感じていないことがあります。
これまでは、現場での労働力不足を補うため、外国人労働者の雇用を増やすなどの対処療法でしのいできました。しかし、今では海外に比べた給与水準の低さと円安によって外国人労働者も集まらなくなってきています。さらに、設計、施工管理など現場作業以外の部分でも人不足や高齢化が進み始めており、対処療法的対策では解決不能な状況になってきています。
また、ビジネスとしての建設業の生産性が他業種より低いことも課題です。日本建設業連合会の調査によると、2021年における建設業の生産性は2944円/人・時間でしたが、これは全産業の平均生産性の4521円/人・時間に比べるとはるかに低い水準です。この点は、建設業に非効率な仕事の進め方が定着していることを示唆しています。実際、2021年度における全産業の平均年間実労働時間は1633時間でしたが、建設業界の年間実労働時間は1984時間と長く、就労者に大きな負担が掛かっている状態です。
さらに、対応すべき課題として挙がってきたのが脱炭素化です。2015年には、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」、通称、建築物省エネ法が公布されました。エネルギー消費性能への適合に向けた措置が定められており、2025年には、新しい建築物すべてに対して適用されます。近年では、建設会社自身が排出するCO2だけではなく、工事を下請け、孫請けする企業、さらには建築物で使用する建材や住宅設備のサプライヤが生産・輸送する際の排出量の削減も求められるようになりつつあります。
価値観や知見が異なる全関係者が課題共有しないと建設DXは実践できない
これらの課題を解決するための手法のひとつとして、建設業界の各企業では、建設DXの実践を推し進めています。クラウドやAI、IoTなど最新の情報通信技術を活用し、業務に潜む無駄を洗い出し人手不足への効果的な対処や生産性を向上させようとする活動です。さらに、建設業務の内容や、建物を構成する建材・住宅設備などの生産・輸送履歴などを“見える化”すれば、脱炭素化の取り組みにも繋がります。
業界構造から見て、建設業界の最大の特徴は、ひとつの建物を建てる際に、さまざまな役割を担う数多くの企業や人が関わることです。施主やデベロッパー、設計事務所、建設会社以外にも、専門性の高い仕事を引き受けるさまざまな施工協力会社が関与し、さらには建材や住宅設備を供給するサプライヤも関わってきます。こうした複雑な業界構造が、人手不足の解消を困難にし、生産性の低下を招き、効果的な脱炭素化を阻害している面があります。
その一例を挙げましょう。建設現場で何らかの不具合が起きた場合、その場所の施工や使われている建材供給に関わった関係者が一同に集まることがよくあります。現場を見ながら対処策を擦り合わせるためですが、現場で解決できなければ、それぞれ課題を自社に持ち帰り、解決策を持ち合って再度擦り合わせることになります。これは、日本の建設業界が誇る、高い安全性と品質を担保する「現場主義」に基づく作業なのですが、人手不足の解消や生産性向上といった観点から見れば、無駄が多い作業とも言えます。これからは、現場主義の良い面を維持しながら、作業効率を高められる方策の導入が必須になってきます。
建設DXは、こうした建設業界固有の事情を勘案しながら実現を目指す必要があります。ただし、いざ解決策を探ろうとすると、一筋縄では解決できないことに気付きます。建設に携わる、多様かつ多くの関係企業・関係者全員が、建設DXによる課題解決の重要性を共有し、その実践を許容して、足並みを揃えて協力する体制が求められるからです。
日本の建設業界は、世界に比べてデジタル技術を活用した業務改善などへの取り組みが遅れている傾向があります。特に現場では、紙に書かれた設計図面を読み下し、必要な建材を組み上げ、その場で加工することに慣れ親しんだ技能者のチカラを借りなければならない場面が多いため、デジタル技術の導入に抵抗感を感じる人が多くいます。脱炭素化に向けた取り組みにおいても、建材や住宅設備を供給するサプライヤ各社が、自社製品の生産・供給でのCO2排出量のデータを公開する必要があり、それにはこれまでとは異なる協力体制の構築が求められます。
建設DX実践のプラットフォームとなるBIM/CIM
建設DXを推し進める上での入り口となるのが、BIM(Building Information Modeling)もしくはCIM(Construction Information Modeling)の導入です。
BIM/CIMとは、建設する建物を3D CAD上の3Dモデルとして設計し、3Dの図面として描かれる「形状情報」と、その形状のモノがどのような建材でいかなる構造なのかといった「属性情報」を紐付けて記録しておく、建物に関する情報を関係者が共有し集中管理するためのデータベースです。BIM/CIMを活用すれば、計画・調査・設計・施工・管理の各段階で、それぞれの担当者が正確に情報を共有できるようになります。また、3Dモデルをクラウド上に置いておけば、現場に関係者が集まらなくても、同じデータを参照しながら、リモート環境で不具合の解決を擦り合わせることが可能になります。

BIM/CIMの活用には、建設に関わる作業を効率化する、さまざまなメリットがあります。まず、3Dモデルから図面を切り出して意匠・構造・設備などの図面を作成できます。同じデータから切り出しているため、それぞれが連携しており、切り出した後の図面間で整合性が維持されており、人的ミスの発生を防止します。
また、形状情報と属性情報を活用し、それを集計することで、床面積や建材の必要量などを簡単に計算できます。さらに一歩進んで、データを各種解析ソフトと連携させれば、日陰や換気、温熱環境、空調、風環境、都市計画の影響など、さまざまなシミュレーションを実施することも可能です。加えて、3Dモデルを施主などに向けたプレゼン用のパース・動画の作成に利用できるため、設計後の様子をイメージで伝えやすくなります。こうしたメリットをフル活用すれば、人手不足や低い生産性といった課題の有効な解決策となることでしょう。
さらに今後、BIM/CIMの属性情報のひとつとして、生産や輸送、さらには現場での加工に際してのCO2排出量の情報が盛り込まれるようになる可能性が高いようです。既に製造業の領域ではそうした動きが出てきており、自動車など工業製品のライフサイクルを一元管理するPLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)環境の中で、製品を構成する部材を供給するサプライヤや物流業者が、CO2排出量の情報を管理する方向に向かっています。現時点で建築業界において具体的な動きが顕在化しているわけではありませんが、こうした他業界の動きを見て、自社での対応を検討し始めています。
その一方で、建築物にかかわるエネルギー消費の多くは運用時に排出されます。運用時のエネルギー消費低減に向けて、建物のMEP(機械・電気・配管)の運用データをBIM/CIMのモデルに適用することによって、運用時の脱炭素化に向けた対策効果をシミュレーションし、適切な低減策を見つけ出すために利用する検討も始まっています。
公共事業の工事に関わる企業へのBIM/CIMの導入が原則義務化
建設業界が健全に成長していくことは、日本経済の成長と豊かな社会の実現に向けた重要な要素です。2016年、国土交通省は、日本での建設DXの実践を加速させるため、「ICTの全面的な活用」「規格の標準化」「施行時期の標準化」の3つの施策を柱として掲げる「i-Construction」と呼ぶプロジェクトを開始しました。

さらに、2020年4月には、「2023年までに小規模を除く全ての公共事業にBIM/CIMの原則適応を求める」と発表しています。先述したように、建設DXは、多くの建設関係企業が足並みを揃えて対応していかないと効果が出にくい特徴があります。業界全体が、建設DXに向けて腰を上げる環境を作るために、公共事業をテコに使った格好です。今後は、BIM/CIMを中心に据えた建設DXが急速に進んでいくことでしょう。
現時点でBIM/CIMに入力しているデータは、設計時に用意するものが中心です。今後は、IoTデバイスでの現場データの収集やドローンでの3次元測量など、新たな技術を活用して、施工中に現場で収集したデータをBIM/CIMの3Dモデルに入力。建設過程での作業記録や検査結果、注意事項などを時間情報と共に記録すれば、建物が完成した後、運用が始まってからも効果的で効率的な管理・メンテナンスに利用できるようになります。人工知能(AI)などより高度な解析技術を適用することで、不具合が発生する前に劣化や故障の兆しを察知して計画的に補修・修繕する予知保全も可能になるかもしれません。
建設業界が抱える課題を解決するために推し進めている建設DXですが、将来は、建設業界での新たな価値創造に利用されていくことになりそうです。
※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。
※本文中に™ および ® マークは表記していません。
プロフィール
伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表
技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。