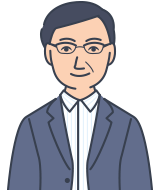- 詳細解説
- 業界別IoTシステムの活用例
第3回
エッジAIで高度化する近未来のスマートファクトリ
昨今、生産性向上を目指す施策として、工場でのデータ利用が活発化しています。
操業データを収集するIoT(Internet of Things)と、データから価値ある情報を抽出するAI(ML、DL、ルールベース)を組み合わせたシステムに加え、生産現場でデータの解析処理を完結させるエッジAI(組込みAI)の活用も進んできました。
この記事では、先進的なスマートファクトリの構築が進む半導体産業と自動車産業を例に挙げ、AI活用のトレンドを解説します。さらに近年、特にエッジAIの利用が進んでいる理由と利用シーンを説明し、将来の工場での生成AI活用の可能性についても触れます。

近年、「生成AI」と呼ばれるより進化した人工知能(AI)が実用化され、人と自然な言葉で対話しながら効率的に調べごとをしたり、出来上がりのイメージを伝えるだけで自動的に精緻なイラストが描けるようになったりしたことで、驚いている方も多いのではないでしょうか。「ChatGPT」や「Stable Diffusion」などのサービスを実際に利用して、その威力を実感している人も少なくないことでしょう。
人と機械の間で情報を伝達する役割を担うヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)も進化し、自動運転車などでは高度な画像認識や言語処理を駆使するようになりました。家電製品やIT機器がユーザー傾向を学習する例は、もはやめずらしくありません。
こうしたAI技術の進化や実用化の恩恵を受けているのは、パソコンやスマートフォンで利用するサービスだけではありません。製造業の開発現場や工場、電力網や道路などの社会インフラ、医療システム、ビル管理など、ビジネスや社会活動の領域においてもAIが積極的に活用されています。そして、デジタルトランスフォーメーション(DX)をより効果的かつ効率的に進めるために欠かせない手段になっています。
なかでも製造業の工場では特にAIの活用が加速しています。「Quality:品質・仕様」「Cost:コスト・原価」「Delivery:数量・納期」のいわゆる「QCD」を自律管理するため、さらには、少子高齢化による人材不足や継承者不在に、また、カーボンニュートラル達成に向けた脱炭素化を解決するための手段としても利用されています。
IoT+AIをフル活用するスマートファクトリ
AIとIoTシステムを組み合わせることによって、生産活動の自律制御や効率的メンテナンスなどを実現する工場を「スマートファクトリ」と呼んでいます。スマートファクトリでは、生産現場に置かれた装置・設備それぞれに設置したセンサーから、稼働状況や生産仕掛り品(ワーク)の状態などに関するデータをリアルタイムで収集します。収集したデータを蓄積したビッグデータをAIで解析し、効果的なQCD管理や自律的生産の実践に役立つ情報を抽出することで、製造・メンテナンスでの価値向上や効率改善に利用しています。
なかでも特に高度な利用法が見られる分野が半導体と自動車です。一般に製造業は、生産技術の体系が異なる2種類の形態に大別できます。1つは、生産ラインに投入した原料を対象にして、段階的にさまざまな加工を施して製品を作る「プロセス型製造業」。もう1つは、多種多様な部品材料を組み合わせて複雑な製品を作る「アセンブリ型製造業」です。そして、プロセス型製造業の中で最も高度な生産技術が求められているのが半導体であり、アセンブリ型製造業の中で最も高度なのが自動車です。
この2つの産業に投入される生産技術は、高度であり、さらに産業規模が巨大で新たな技術導入が進みやすいことから、いずれ他の産業にも展開される可能性が高いと言えます。
例えば、「トヨタ生産方式(TPS)」として知られる部品材料の在庫や仕掛品を最小限に抑える「ジャスト・イン・タイム(JIT)」での生産は、「リーン生産」として一般化され、他産業の工場にも展開されるようになりました。半導体工場の生産方式に関しても同様の傾向があります。
AI活用の未来を先取りしている半導体工場と自動車工場
これら2つの産業でのAI活用の状況を、より具体的に見てみましょう。
半導体工場の中でも特に最先端の工場では、求める性能のチップを採算が取れる歩留りで生産するために、AIやIoTを駆使しています。クリーンルーム内でチップを製造している半導体工場では、人が汚染源となってしまうため、元々製造工程の自動化が進んでいる分野でした。そこで利用されるAIやIoTは、省人化が目的ではなく、自律化した工程をさらに高度化する目的で活用される傾向があります。
数万工程を使い分けて数十品種のチップを製造しているある半導体工場では、工場内に置かれた5000台以上の製造・検査装置、自動搬送システムなどから1日当たり約20億件ものデータを収集し、生産管理やメンテナンスなどに活用しています。最先端の半導体チップの生産難易度は極限まで高まっており、ワークの微妙な出来の違い、製造・検査装置の個体差や経時変化が、チップの品質や歩留りを大きく左右します。利益を上げるためには、収集した莫大な量のデータをリアルタイムで解析し、装置の設定条件や稼働スケジュールを最適化したり、個々の装置・設備に最適な加工条件をフィードバックしたりすることが必須になっています。
蕎麦打ち名人は、そば粉の状態や天候の変化に応じて、加える水分の量やこね方を変えて品質を維持すると言われていますが、半導体工場では同様の作業をケタ違いに大きな規模で行っていると言えます。しかも、装置・設備の条件を最適化するだけでなく、ライン全体で生産活動を最適化する必要があるのです。ビッグデータを基にこうした判断を下す際には、人の知的能力では手に余す状況になっており、AIを活用した迅速・正確な判断が求められます。

一方、自動車工場では、これまで人手に頼っていた作業を自動化することを目指したAIやIoTの導入・活用が進められています。特に、キメ細かな作業対応をしていた職人技を自動化・自律化することが導入の動機となる傾向があります。
例えば、ボディの塗装工程での色味合わせは職人技が求められていた作業の典型です。完成車のボディの色は、組み合わせる部品の材質を問わず同じである必要があります。ところが、樹脂製部品と金属製部品では、同じ塗料を使っても発色が異なるのが普通です。これまで、こうした場合の色合わせは、経験豊富なベテラン作業員の経験と勘に頼っていました。これが今では、部品ごとの色の微妙な違いの判別にAIを利用することで、機械による高精度な色味の検査・管理と、塗装装置の最適設定が可能になってきました。
同様の職人技が求められる工程は、ボディのプレス成形や射出形成、溶接、ラインの生産スケジュール作成、装置・設備のメンテナンスなど、数多くあります。そして、こうした属人的なスキルに頼る生産は、人材不足や技術継承不安から、おしなべて持続可能ではなくなってきました。その1つひとつで、AIとIoTを活用した職人的スキルのシステム化が望まれ、導入が進められています。現在では、さらに進んで、生産ライン上の装置・設備の機能や個体差、個々の状況を反映させたコンピュータ・モデルを構築し、AIで解析した情報に基づいて最適化した稼働条件などを、仮想的に検証する「デジタルツイン」の仕組みも構築・運用されるようになりました。

スマートファクトリでのAI活用では、“学習”はデータセンターで“推論”は現場
スマートファクトリでのAI活用には、AIの実装方法において、パソコンやスマートフォンなどで利用するサービスとは異なる潮流が見られます。パソコンやスマートフォンではAI関連処理をクラウドに集中させるのに対し、スマートファクトリでは、“学習”と“推論”というAI処理の2つの構成要素のうち、学習はデータセンターで実行し、推論は現場に置かれた装置・設備に組込まれた「エッジAI」を利用する例が多いことです。

学習処理に関しても、学習に求められる演算能力が莫大であることからエッジAIの利用は無理でも、オンプレミスまたはプライベートクラウドの活用が求められる例が多くあります。また、学習に用いるデータも、現場で収集した生データをそのまま利用することは少なく、現場で加工やスクリーニングを行ってから転送するのが一般的です。パソコンなどで利用するAIサービスでは、学習と推論の両方の処理をパブリッククラウドで行う例がほとんどです。
スマートファクトリでエッジAIによる推論処理が求められる理由は大きく3つあります。
1番目の理由は、リアルタイムでの推論処理が求められること。装置の稼働状況やワークの検査結果を反映したデータを基にした解析結果を、可及的速やかに装置・設備の最適制御へとフィードバックしたいからです。クラウドに収集したデータを転送すると相応の遅延時間が発生することは避けられませんが、エッジで推論処理を行えば遅延を最小化できます。
2番目の理由は、AIシステムの構成の単純化と運用の低コスト化。例えば、カメラで撮影した映像データを対象にして溶接後の品質を検査する場合、映像データのような大容量のデータをクラウドに転送すると、大容量の通信システムの整備と高コストのデータ通信サービスの利用が必要になってきます。エッジで推論処理を実行できれば、こうした通信の大容量化を避けることができます。
3番目の理由は、セキュリティレベルを高めることです。工場で扱っている生産関連のデータは機密性の高い内容のものがほとんどです。このため、公衆回線経由で生データをパブリッククラウドに転送するようなことは、セキュリティの観点から憚られます。これは、メーカー自身の競争力を維持するためにも必要な配慮ですが、受注生産などを行っている工場でも顧客の情報を漏らさないために必要になってきます。
製造業以外でも、これら3つの理由からエッジAIの活用が求められている領域が多くあります。例えば、家電製品や業務用機器、医療用機器、社会インフラ用の機器・設備です。このため、エッジAIの利用市場は、2020年から2025年に掛けての年平均成長率26%と急成長すると予測されています。
課題解決に向けたエッジAI対応マイコン
スマートファクトリの構築に欠かせないエッジAIですが、これまで装置・設備の管理・制御に使われていた汎用性の高いマイコンでは、推論処理の実行には演算能力が足りないのが普通です。エッジAIに対するニーズの高さを背景にして、マイコンメーカー各社はエッジAI対応の新型マイコンを次々と開発し、市場投入しています。こうしたエッジAI対応マイコンには、大きく2つの技術が投入されています。
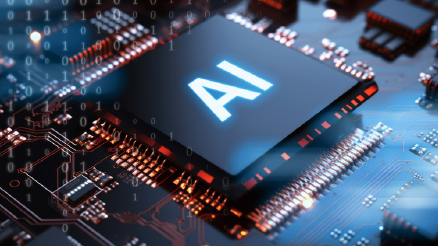
1つは、推論処理に最適化した仕様の演算器で構成したAIアクセラレータの搭載です。例えば、画像認識に利用するAIの推論処理には、一般的な画像処理アルゴリズムよりも2~3ケタ高い積和演算性能が必要になります。このレベルになると、ハイエンドの組込み用マイコンであっても処理が困難です。ただし、一般に、推論処理は8ビットの固定小数点演算といった低精度の演算で十分です。現代のマイコンに搭載されている32ビットの汎用演算器や浮動小数点DSPは不要ですし、ニューラルネットワークを最適化すれば、さらに低精度にすることも可能です。演算器を低精度化した分を並列度の向上に回せば、効率的に演算性能を高めることができます。
推論処理の一部には積和演算以外の処理も含まれており、そこではアプリケーションごとに異なる処理内容を実行することになります。マイコンメーカーの中には、FPGAのようなプログラムで専用回路を構成できるコアを搭載し、必要に応じた内容の専用回路を動的に構成するDRP(Dynamically Reconfigurable Processor)と呼ぶ技術を導入して、柔軟性と高性能化を両立させようとするところも出てきています。
もう1つは、メモリーと演算器の間でのデータ転送を最小化するアーキテクチャの採用です。一般に、現在のマイコンなどでは、処理を実行する度に、プログラムのコードや処理対象となるデータをメモリーから演算器に転送する、ノイマン型のコンピュータアーキテクチャが採用されています。ところが、AI処理では、このデータ転送がこれまで以上に多く発生し、演算性能を向上させるうえでのボトルネックになってしまいます。そこで、メモリーと演算器の間の論理的距離や物理的距離を近付け、転送時間を最小化しようとする技術の導入が進んでいます。具体的には、データ圧縮やメモリーインタフェースの改善、さらにはメモリーアレイ内のセルのそばに並列度を高めたコアの1つひとつを分散配置する「IMC(In-memory computing)」と呼ぶアーキテクチャの採用などが検討されています。
早くも出てきた工場での生成AI活用の動き
また早くも、スマートファクトリで生成AIを利用して、さらに高度な自律操業を可能にしようとする動きも出てきています。生成AIには、自然言語やプログラム言語など言語系の処理に強いChatGPTなどに利用されている「基盤モデル(Fundamental Model)」をベースにしたものと、画像や動画の自動生成に適用されるStable Diffusionなどに利用されている「拡散モデル(Diffusion Model)」をベースにしたものがありますが、それらいずれにおいても工場で利用する動きが出てきています。
生成AIを活用する目的は2つあります。1つはオペレータからの自然言語によるあいまいな指示に基づく適切な機器制御、もう1つは画像データと言語、センシングしたデータといった複数種類のデータを勘案して適切な判断を下すマルチモーダルAIの実現です。
現在、アセンブリ型製造業を中心に、人間と機械が高効率に連携する生産ライン作りが求められるようになってきています。そうしたラインの構築では、人から出される指示を受けて、適切に動ける機械が必要になってきます。ここに基盤モデルをベースにした生成AIを適用し、人と機械の連携を密にするための技術開発が進められています。

あらかじめ時間を掛けて大量のデータでキッチリとした基盤モデルを作っておくことで、わずかな学習で従来のディープラーニングよりも精度が高いAIを実現できます。このため、オンプレミスでの学習処理を適用しやすくなる可能性があると考えられます。
また、工場内では、複数の作業員が同じ装置やワークを見ながら、指示し合うような場面が多くあります。こうした場面で作業の一部を機械化するには、映像データと自然言語を参照しながら適切な行動をとる能力が必要です。拡散モデルを適用して、そうした処理を実現しようとする動きが出てきています。動画を自動生成するAIが登場していますが、これと同じ技術を利用して、あいまいな指示に応じて機械やロボットの行動を自動生成するのです。
AIは、ディープラーニングから生成AIに進化し、将来は汎用AIへとさらに成長していくことでしょう。こうした中で、より多様な情報を基に、多面的な観点から、さまざまな処理・作業の判断に適用できる、高度化・汎用化・高精度化が進んでいくとみられています。これに伴って、スマートファクトリでの活躍の場は、ますます拡大していきそうです。
※このWebサイトで使用している会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。
※本文中に™ および ® マークは表記していません。
プロフィール
伊藤 元昭氏 株式会社エンライト 代表
技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。